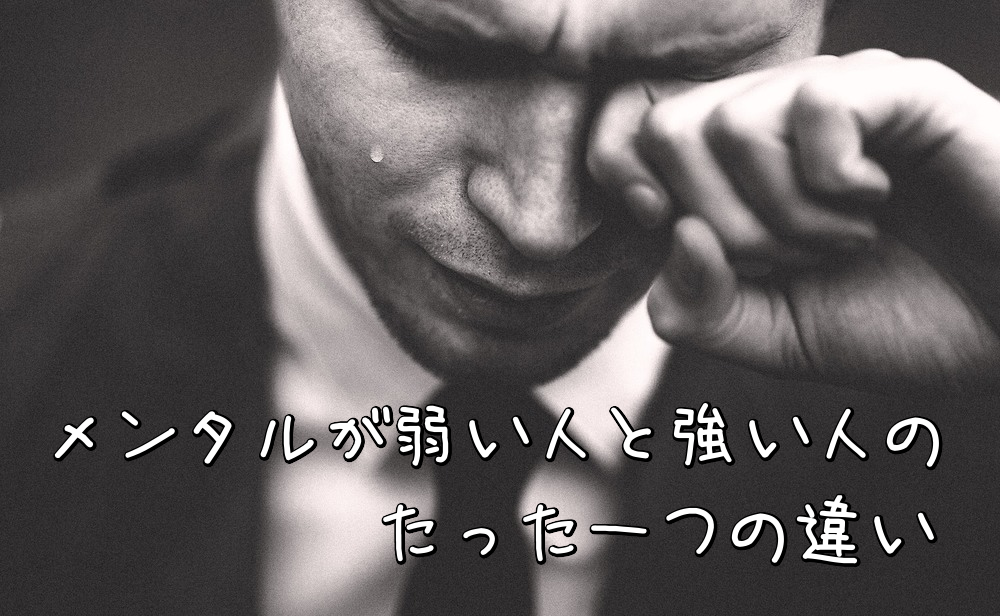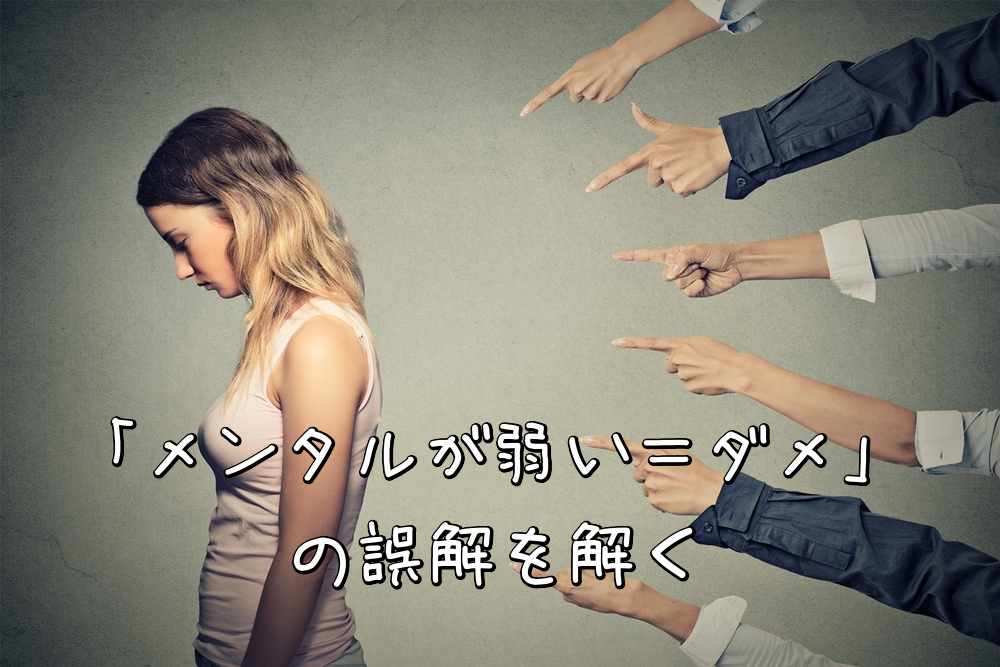対策自分論
ふゆこさんの記事「原因自分論って対策自分論じゃないだろうか」を読み、「これはいいな」と思いましたので、ご紹介します。
ふゆこさんは「原因自分論」というネーミングに違和感を持ち、「対策自分論」という言葉のほうが本質をとらえているのではと指摘しています。
彼女は「過去―未来」と「他人―自分」の2軸で、変えられる領域と変えられない領域を整理していて、これって、まさに境界線を引くことそのものです!
「原因自分論」という言葉だと、あたかも「すべての原因が自分にある」と誤解されがちです。
でも、自分の性質は、自分が望んで選んだものではありません。
性質的なものに対して「自分の責任だ」と思い込んでしまうと、それは不健全な自己否定につながってしまいます。
だからこそ、「変えられるところ」と「変えられないところ」を見極め、変えられる部分にフォーカスすることが重要です。
うまく対策するために必要なこと
努力には、「報われる努力」と「報われにくい努力」があります。
自分の変えにくい部分を無理に変えようとする努力は、なかなか報われません。
変えられる領域に向けた努力こそが、報われる努力につながります。
とはいえ、現実には「変えられる領域」に焦点を当てるのは意外と難しい。
その大きな原因の一つが、
**「自分のありのままを受け入れられていないこと」**です。
ありのままを受け入れると、対策は機能する
自分をありのまま受け入れられる人は、対策自分論を自然に活用できます。
「今の自分の状態」と「理想の状態」を把握し、そこに向かうための道筋を考えて、努力するだけです。
このステップは、生成AIを使うと非常にスムーズになります。
現状と理想を入力すれば、適切な対策や行動計画を提案してくれます。
…とはいえ、ここにも落とし穴があります。
難しいのは「現状」と「理想」の正確な把握
実は多くの人にとって一番難しいのは、実行よりも、正確な現状認識と理想の把握です。
根底に自己否定がある人は、自分の現状を正確に見ることができません。
- 自分を過小評価する
- あるいは、無意識に過大評価してしまう
- 理想が高すぎたり、心から望んでいない理想を目指してしまう
…こうした「ゆがんだ現状認識」と「ゆがんだ理想」をベースにした対策は、もはや意味を持ちません。
だからこそ、まずは「現状と理想をありのままに修正するプロセス」が重要になります。
『ワールドトリガー』28巻に学ぶ「ありのままの受容」
このテーマについて、深く参考になったのが
漫画『ワールドトリガー』28巻です。
ここで描かれる若村麓郎というキャラクターは、「無能だと思われること」への強い恐れを持っていました。
彼の現状認識は「自分は無能ではない」
理想は「自分が有能であると証明したい」
この思いが強すぎて、無理な理想に挑戦して失敗したり、失敗を恐れて挑戦そのものを避けてしまいます。
その結果、何も得られず、時間だけが過ぎ、自己肯定感がすり減っていく――
作中ではこうも描写されています:
「自分の頭で考えることと外に知識を求めることはどっちもバランス良く必要なんだけど、麓郎はかなり外に偏っているんだよね。いろんな人に助言をもらいに行くのはいいんだけど、助言をかみ砕いて受け止めるための器がないんだ」
つまり、自分の無能さを恐れるあまり、外からの助言も受け入れられない。
そのため、成果につながるものが何も残らない。
しかし、彼はある場面でこう気づきます:
「…今 やっと気付いた オレは…怖えぇんだ…
自分が本物の無能だってわかるのが…」
「怖えぇから もっと手前で負けようとしてたんだ
怖えぇから 他人の『答え』を追い続けてたんだ」
この気づきこそが、ありのままの自分を受け入れるための第一歩です。
正しい現状認識の先にあるもの
ここに気づき、逃げずに向き合い、負の感情を消化するプロセスを経て、ようやく人は「本当の自分の理想」を見出すことができます。
- 自分がどうありたいか
- どんな人生を送りたいのか
- 何をやりたいのか
これらが、おぼろげながら見えてくるようになります。
そして、ここでようやく**「対策自分論」が真に機能する**のです。
努力が報われるとき
ここまで来ると、努力が報われるようになります。
そして、たとえ理想がまだ達成されていなくても、「自分が恐れていたこと」には、もう振り回されなくなる。
それが、ありのままを受け入れることの力です。
さいごに
「ありのままを受け入れること」について、私自身、うまく言語化したいと思っていたのですが、ワールドトリガーの作者が、それを描いてくれました。
この漫画はカウンセリング本ではありません。
しかし、その用途として、最上級の教材だと感じています。